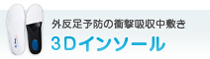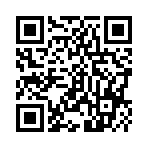2014年07月27日
第二回子どもボクササイズ体験報告
7月の体験活動は、子どもボクササイズでした。
からだ環境総研では、子ども達が非日常体験をすることにより生きる力の向上や自己制御機能への発達につながればと月に1度程度行っています。
今まで経験したことが無いことにチャレンジするということは予期せぬ事態に自分で考えどう対応していくか?
という点で今回も初めての事への挑戦は、おっかなビックリのところもあったようで最初はかなり緊張気味でしたね。
今回の女子プロボクサーで世界チャンピオンの黒木優子選手がコーチを務めてもらったことで、お母さん達も大喜び。

ラダートレーニングでは、今までやった事のない動きに最初は戸惑っていましたが 神経が発達途上にある子どもは繰り返しチャレンジすることで
身体の使い方がかなりスムーズになり動きも整ってきました。

3分間の縄跳びでは、黒木コーチの跳び方を真似るがどうしても高く飛びすぎて3分間連続できない事がありました。
(これは、夏休み中の課題となりました。)

鏡の前でのシャドーボクシング。

ここでは、見学のお母さんたちも一緒に、基礎的な構えとフックやストレートの出し方、フットワークや呼吸法などを中心に行い
ボクシングらしい形になってきました。
前回は男の子ばかりでしたが、今回は女の子も参加。そのリズム感の良さには脱帽でした。
そして、いよいよボクシンググローブを付けサンドバックへ

今までシャドーボクシングでやってきたことをサンドバックで試してみました。

パンチを出し時に、シャドーでは経験しなかった相手との距離間の大切さを身をもって体験したようで
一番力が入る距離を自分で工夫していましたね。
「人に言われなくても自分で工夫する力」というものはこういう体験の場から開発されていくのでしょうね。
そしていよいよリングへ

5.47メートル四方のリングが狭いでしょうか?広いでしょうか?子ども達の第一声は、「せまっ」でしたが
ミニスパーリングでは、
サンドバックと違い相手が動き回るので、相手を射程距離内に入れるむずかしさを体験したようです。
特に黒木選手は、まるで素手で蝶を捕まえる時のように、手を伸ばすとするっと目の前から消えていく、そんな華麗な姿に、見ている大人が惚れ惚れしていました。

運動量はかなりのもの。でも子ども達はトレーナーを自分の射程距離内に入れる為に必死で動き回ります。
相手の動きを詠みうまく距離感をつかんだときにジャブを出していきます。

まるで鬼ごっこのような動きにお母さんたちも大爆笑。

でも、そこは子ども達コツをつかむと早いものです。

神経系統の発達は、小学生時期でおおよそ終わってしまいます。
この時期 不規則な動きってすごく大切です。
鬼ごっこは、身近で出来る運動神経UP種目と言ってよいでしょう。
頑張ったご褒美に世界チャンピオンの動きをご披露いただき、
その身のこなしの可憐さとパンチの速さに参加者全員 目が●になってしまいました。
目が●になってしまいました。

2時間びっちり汗をかき、黒木選手・古賀オーナーとの記念撮影。

11月に行われる黒木選手のタイトル防衛戦に応援に行くことを約束して無事終了しました。
黒木選手はこんな可愛いボクサーですよ。
子ども達が成長した頃のわが国は人口減少・超高齢社会の到来やグローバル化、高度情報化、環境・資源問題の深刻化など変化の激しい時代にあります。
こうした変化の潮流を踏まえると、これまでにも増して知・徳・体の調和を図りつつ、問題解決のために豊かな創造力を発揮できる「生きる力」を育てる必要があるのではと思っています。
非日常体験は、こうした未体験化におかれたときの対応能力を養ってくれます。
夏休み期間今までやったことのない事に、是非チャレンジして下さいね。
からだ環境総研の2学期は、再び 走りを早くする方法を開催します。
走る力は様々な運動にからだ作りに関係してきます。初めての方ご参加お待ちしています。
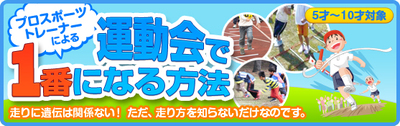
*尚、佐賀市内での走り方教室もお母様方のご協力で開催に向け準備を始めています。
開催が決まりましたらお知らせいたします。
子どもの体験活動にご興味ある方は、
無料登録はこちらから
事前に会員登録をよろしくおねがいします。
からだ環境総研では、子ども達が非日常体験をすることにより生きる力の向上や自己制御機能への発達につながればと月に1度程度行っています。
今まで経験したことが無いことにチャレンジするということは予期せぬ事態に自分で考えどう対応していくか?
という点で今回も初めての事への挑戦は、おっかなビックリのところもあったようで最初はかなり緊張気味でしたね。
今回の女子プロボクサーで世界チャンピオンの黒木優子選手がコーチを務めてもらったことで、お母さん達も大喜び。

ラダートレーニングでは、今までやった事のない動きに最初は戸惑っていましたが 神経が発達途上にある子どもは繰り返しチャレンジすることで
身体の使い方がかなりスムーズになり動きも整ってきました。

3分間の縄跳びでは、黒木コーチの跳び方を真似るがどうしても高く飛びすぎて3分間連続できない事がありました。
(これは、夏休み中の課題となりました。)

鏡の前でのシャドーボクシング。

ここでは、見学のお母さんたちも一緒に、基礎的な構えとフックやストレートの出し方、フットワークや呼吸法などを中心に行い
ボクシングらしい形になってきました。
前回は男の子ばかりでしたが、今回は女の子も参加。そのリズム感の良さには脱帽でした。
そして、いよいよボクシンググローブを付けサンドバックへ

今までシャドーボクシングでやってきたことをサンドバックで試してみました。

パンチを出し時に、シャドーでは経験しなかった相手との距離間の大切さを身をもって体験したようで
一番力が入る距離を自分で工夫していましたね。
「人に言われなくても自分で工夫する力」というものはこういう体験の場から開発されていくのでしょうね。
そしていよいよリングへ

5.47メートル四方のリングが狭いでしょうか?広いでしょうか?子ども達の第一声は、「せまっ」でしたが
ミニスパーリングでは、
サンドバックと違い相手が動き回るので、相手を射程距離内に入れるむずかしさを体験したようです。
特に黒木選手は、まるで素手で蝶を捕まえる時のように、手を伸ばすとするっと目の前から消えていく、そんな華麗な姿に、見ている大人が惚れ惚れしていました。

運動量はかなりのもの。でも子ども達はトレーナーを自分の射程距離内に入れる為に必死で動き回ります。
相手の動きを詠みうまく距離感をつかんだときにジャブを出していきます。

まるで鬼ごっこのような動きにお母さんたちも大爆笑。

でも、そこは子ども達コツをつかむと早いものです。

神経系統の発達は、小学生時期でおおよそ終わってしまいます。
この時期 不規則な動きってすごく大切です。
鬼ごっこは、身近で出来る運動神経UP種目と言ってよいでしょう。
頑張ったご褒美に世界チャンピオンの動きをご披露いただき、
その身のこなしの可憐さとパンチの速さに参加者全員
 目が●になってしまいました。
目が●になってしまいました。
2時間びっちり汗をかき、黒木選手・古賀オーナーとの記念撮影。

11月に行われる黒木選手のタイトル防衛戦に応援に行くことを約束して無事終了しました。
黒木選手はこんな可愛いボクサーですよ。
子ども達が成長した頃のわが国は人口減少・超高齢社会の到来やグローバル化、高度情報化、環境・資源問題の深刻化など変化の激しい時代にあります。
こうした変化の潮流を踏まえると、これまでにも増して知・徳・体の調和を図りつつ、問題解決のために豊かな創造力を発揮できる「生きる力」を育てる必要があるのではと思っています。
非日常体験は、こうした未体験化におかれたときの対応能力を養ってくれます。
夏休み期間今までやったことのない事に、是非チャレンジして下さいね。
からだ環境総研の2学期は、再び 走りを早くする方法を開催します。
走る力は様々な運動にからだ作りに関係してきます。初めての方ご参加お待ちしています。
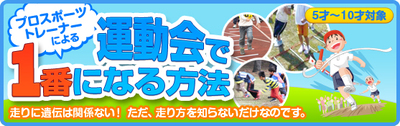
*尚、佐賀市内での走り方教室もお母様方のご協力で開催に向け準備を始めています。
開催が決まりましたらお知らせいたします。
子どもの体験活動にご興味ある方は、
無料登録はこちらから
事前に会員登録をよろしくおねがいします。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。